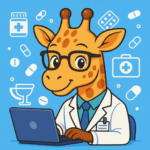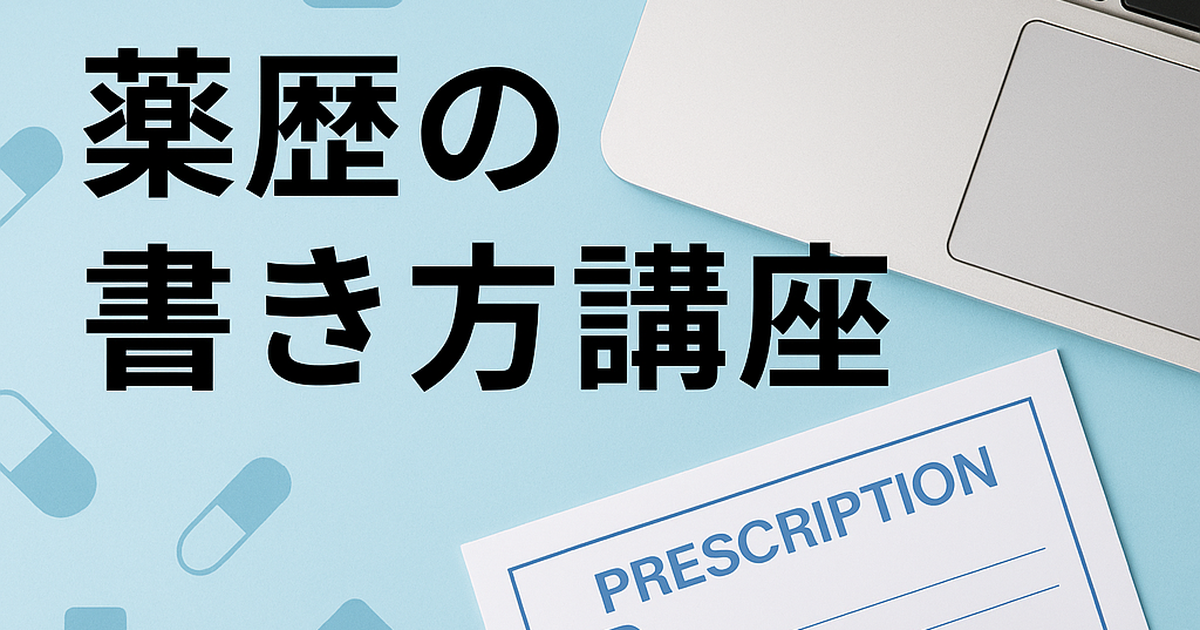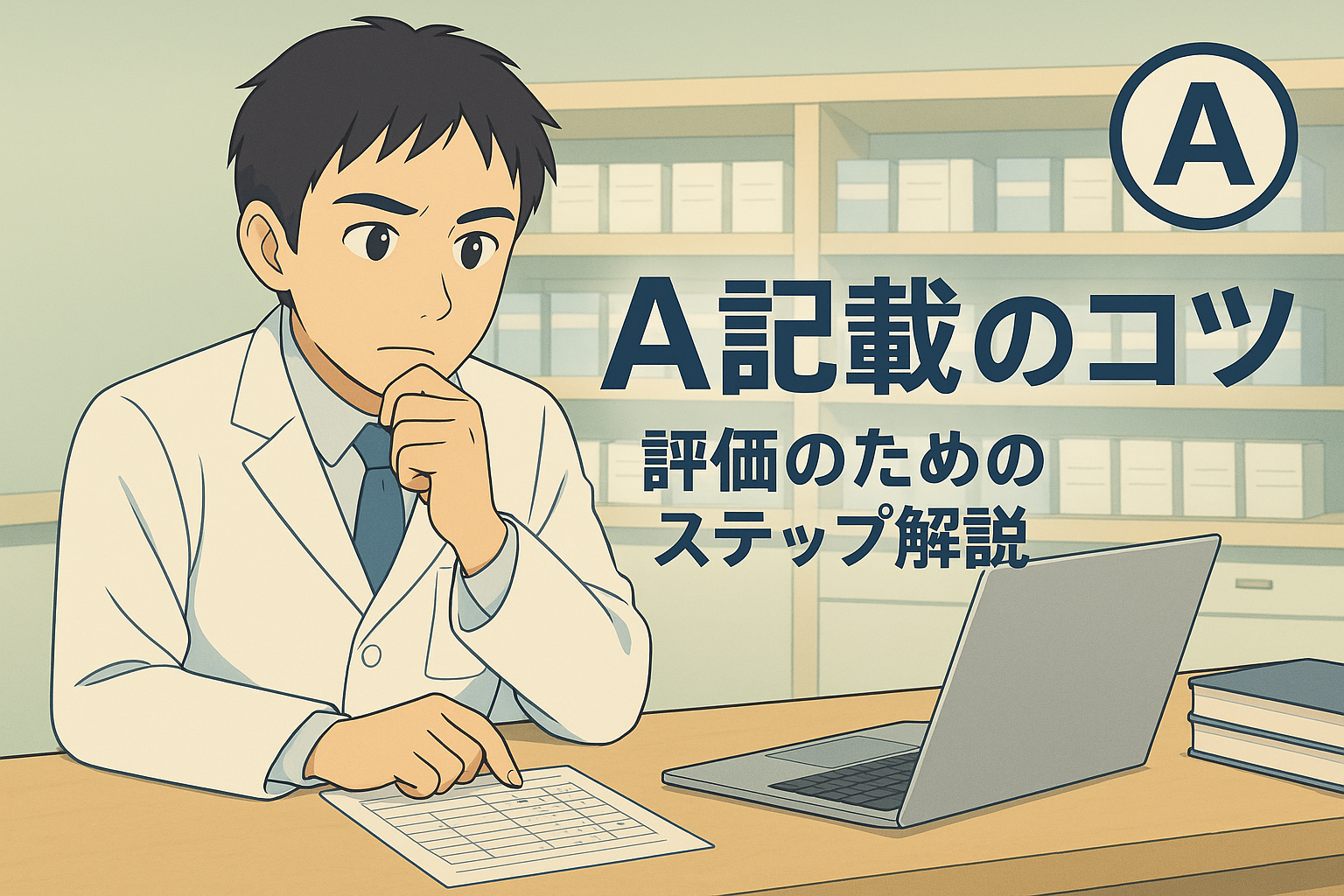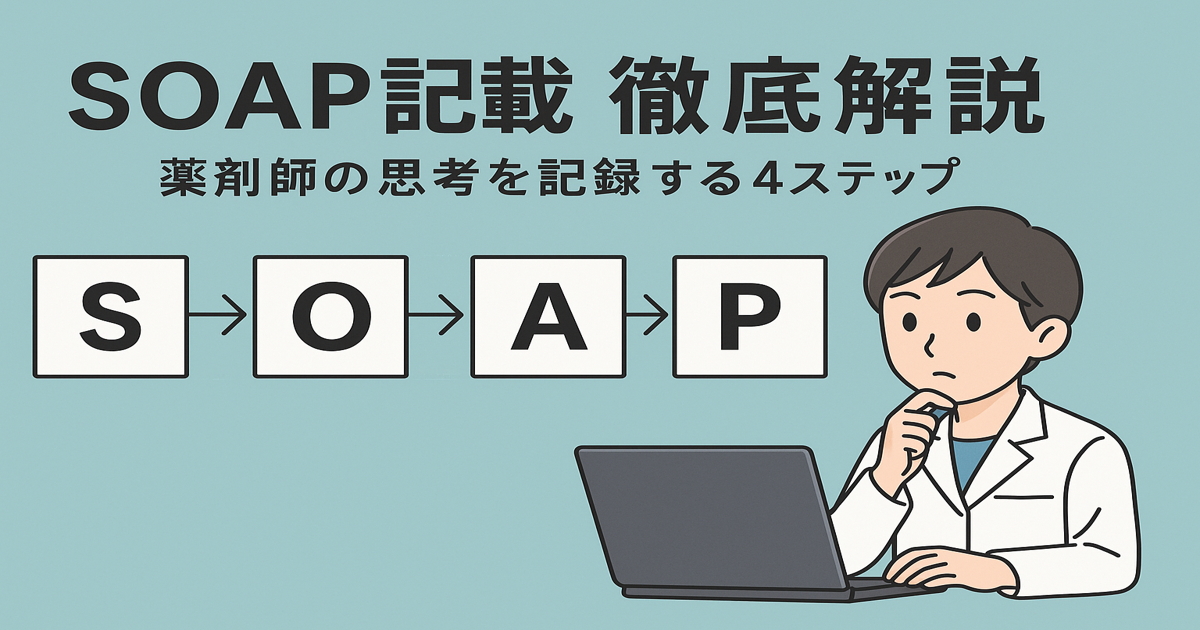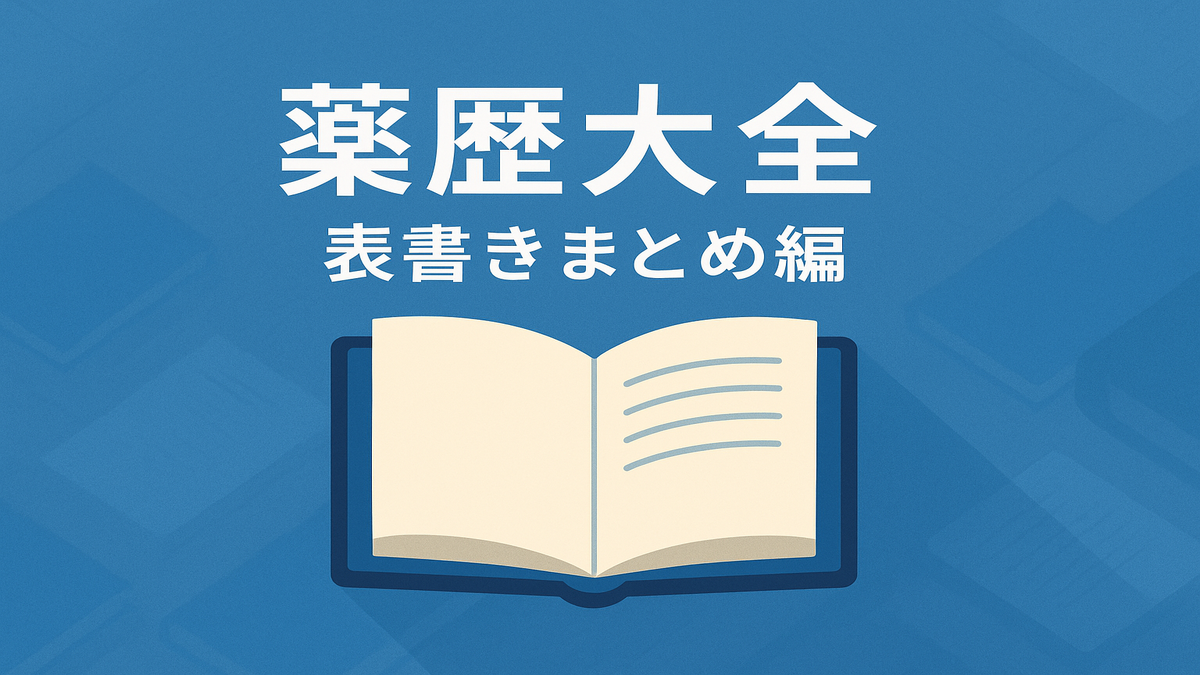【O記載のコツ】SOAP形式で薬剤師が“客観的視点”を磨く方法とは?
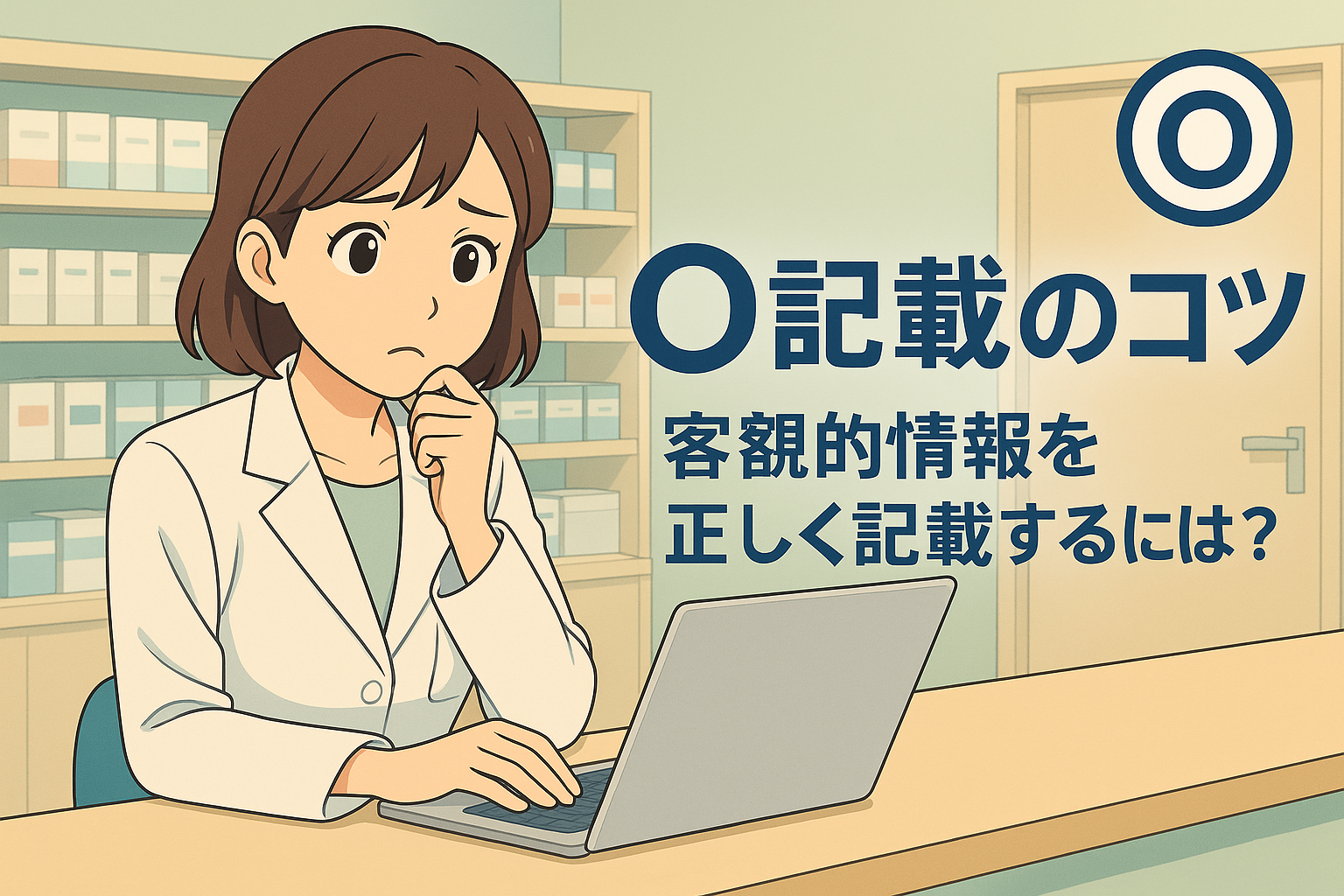
O記載、“自動入力だから大丈夫”になっていませんか?
最近の電子薬歴システム(PharnesX、Melphin、Musubi、Pharmyなど)では、O記載(客観的情報)のテンプレート入力が当たり前になってきています。バイタルや所見欄が自動で埋まる便利な機能ですが——
実はこれ、「O情報の本質」が抜け落ちる原因にもなっています。
O情報は、薬剤師が患者を“観察”し、“測定”し、“記録”する内容です。
テンプレに頼りすぎると、「その人にしかない重要な情報」が曖昧になり、薬歴全体の質も下がります。
- 「Oってバイタルだけじゃないの?」
- 「SとOの違いがよくわからない…」
- 「電子薬歴に自動入力される情報しか書いていない」
もしひとつでも当てはまったなら、この記事の内容を実践してください。
前回の記事をまだ読んでいない方はこちらからご覧ください。
▶【S記載のコツ】“患者の言葉”をどう記録する?聞き取りから要約の技術
本記事では、薬剤師としてO記載をどう捉え、どう記述するかを解説します。
SとOの違いの判断基準から、O記載に含めるべき具体的な情報の種類、よくあるNG例と記載例まで、実践的な内容をお届けします。
O記載のスキルは、SOAP全体の質と、あなた自身の“観察力”を底上げします。
現場での記録がもっと自信を持って書けるよう、ぜひ最後まで読んでみてください。
O記載とは?薬剤師が押さえるべき基本と判断のポイント
O(Objective)=客観的情報とは?
O記載は、誰が見ても同じように確認できる「客観的な情報」を書くパートです。
薬剤師だけでなく、他の医療職が見ても情報の意味が一致する内容であることが重要です。
例えば、次のような情報はOに含まれます:
- 服薬関連:残薬数、服薬状況、副作用の有無、併用薬、他院処方、処方変更内容など
- 身体情報・検査値:血圧、血糖値、SpO₂、体重、NRS、ブリストルスケールなど評価指標
- 行動・所見:ふらつき、皮膚の発赤、表情、姿勢、発語の様子など
- 関係性情報:服薬指導相手(本人・家族・介護者など)、介助状況 など
OかSか、迷うときの判断基準とは?
薬剤師として迷いやすいのが、「これはO?それともS?」という判断です。
ポイントは“情報をどう得たか”です。同じ内容でも、得た手段によってOかSかを変える必要があります。
例:血圧の記録、どっちがO?
- 「患者さんが『家で測ったら140と70だった』と話した」
→ 主観的情報(S)に該当(理由:自己申告のため) - 「患者さんが持参した検査表に“140/70”と記載されていた」
→ 客観的情報(O)に該当(理由:医療記録という裏付けのあるデータのため)
このように、同じ内容でも「情報の出どころ」が違えば、記載区分も変わることを覚えておきましょう。
血糖値や残薬数なども同じです。常に「この情報は誰がどう確認したか?」を意識して書くことが、正確なO記載の第一歩になります。
薬剤師のO記載|書き方のコツと注意点
O情報について前提を揃えたところで、ここからは書き方のコツと注意点をお伝えします。
まず初めに注意すべきポイントを確認いただき、それから各項目の解説に入ります。
- “客観情報”として観察・測定できるものに限定する
- “時系列順”で書く
- 治療と関係のある情報を記載する
1. “客観情報”として観察・測定できるものに限定する
「客観情報を書く」のが原則ですが、実際の記録では“つい主観が混ざる”可能性があります。
薬歴を書いているとき、「これってOに書いていいのかな?」と迷ったことはありませんか?
そんな時は、次のように考えましょう。
書く前に考える3つの問い
- この情報は、自分以外の薬剤師でも同じように記録できるか?
- 数値やスケール、具体的行動として“確認・測定”できたか?
- 感覚・印象に頼っていないか?
O記載は「なにを見たか・測ったか」だけを書く。
「どう感じたか」は、SやA情報として記載する。
この意識を持つだけで、O記載の精度は確実に上がります。
2. “時系列順”で書く
「いまこの瞬間のデータ」だけでなく、“これまでとの変化”を含めて記録することが大切です。
特に検査値やバイタルなどの数値は、単発で見ても判断材料としては不十分なことが多く、“経過”がわかることで初めて意味を持ちます。
例:HbA1cの記録
たとえば、次のような記載があったとします。
HbA1c 6.8
この情報だけでは、他の人が見たときに評価に迷います。これは過去と比べてどうなのかがわからないためです。
では、こう記録されていたらどうでしょう:
HbA1c 6.8(前回7.1、前々回7.4)
このように記載されていれば、経過がひと目でわかり、「コントロール良好」と評価しやすくなります。
O記載では、「いまの状態」だけでなく、「これまでと比べてどうか」も示すことが、評価につながる“価値ある記録”となります。
時系列の視点を忘れずに、数値や所見の変化を意識して記載しましょう。
3. 治療と関係のある情報を記載する
O記載に限らず、SOAP記録全体に共通する大原則があります。
それは、「治療に関係のある情報だけを記録すること」です。
O記載では特に、「なんとなく気になったから」「患者さんの背景を詳しく残しておきたいから」といった理由で、治療と直接関係のない情報を書いてしまうケースがしばしば見られます。
「関係がある情報」とは何か
以下のような内容は、治療の評価・判断・調整に役立つため、O記載に含めるべきです。
- 検査値(血圧、血糖、体重など)とその推移
- 副作用を疑わせる身体所見(発赤、浮腫、咳嗽など)
- 実際の服薬状況(残薬数、自己申告と実物の不一致など)
- 服薬や症状に影響しうる観察事項(会話の応答、ふらつきなど)
一方で、以下のような情報はO記載欄には適しません。
- 趣味に散歩をしており、1日30分歩くようにしている。
- 食事を作るのが面倒で、出来合いのものが好き。
- 家族と疎遠。
これらは患者理解や人間関係の把握には有用な情報ですが、治療判断や服薬アセスメントには直結しないため、必ずしもO記載欄への記載は不要です。
このような患者背景の情報は「表書き」に記載しましょう。
表書きについては別記事で説明しているので、そちらをご覧ください。
▶【表書き大全】個別指導でも評価される“伝わる記録”の書き方と全パターン解説
O記載は、「今日の観察のうち、治療に影響する事実だけを書く場所」と割り切ることで、記録の一貫性が保たれます。
まとめ|O記載が変われば、SOAP全体の質が変わる
この記事のおさらいです。
- O記載は、誰が見ても同じように確認できる「客観的な情報」を書く
- “情報をどう得たか”によってO情報かどうかが変わる
- 時系列の変化や推移も記録し、情報の意味を補強する
- 記載時には“3つの問い”を意識する
O情報はテンプレート通り埋めるだけで終わりではありません。
測定された情報の経過、薬剤師が観察した情報を“根拠のある事実”として記載を残す欄です。
こうした意識をもつと、O情報の質はぐっと上がり、SOAP全体の完成度も一段階レベルアップします。
「なんとなくテンプレで埋めていたO記載」から脱却し、
自分の観察と判断を的確に伝える“実践的な記録”へと昇華させていきましょう。
次回は「A記載の書き方」
次回の記事では、SOAPの“要”となる「A(アセスメント)記載のコツ」について、具体的な考え方・構成・表現のコツを詳しく解説していきます。
▶【A記載のコツ】薬剤師の“思考力”を記録に落とし込むための視点とは?