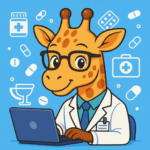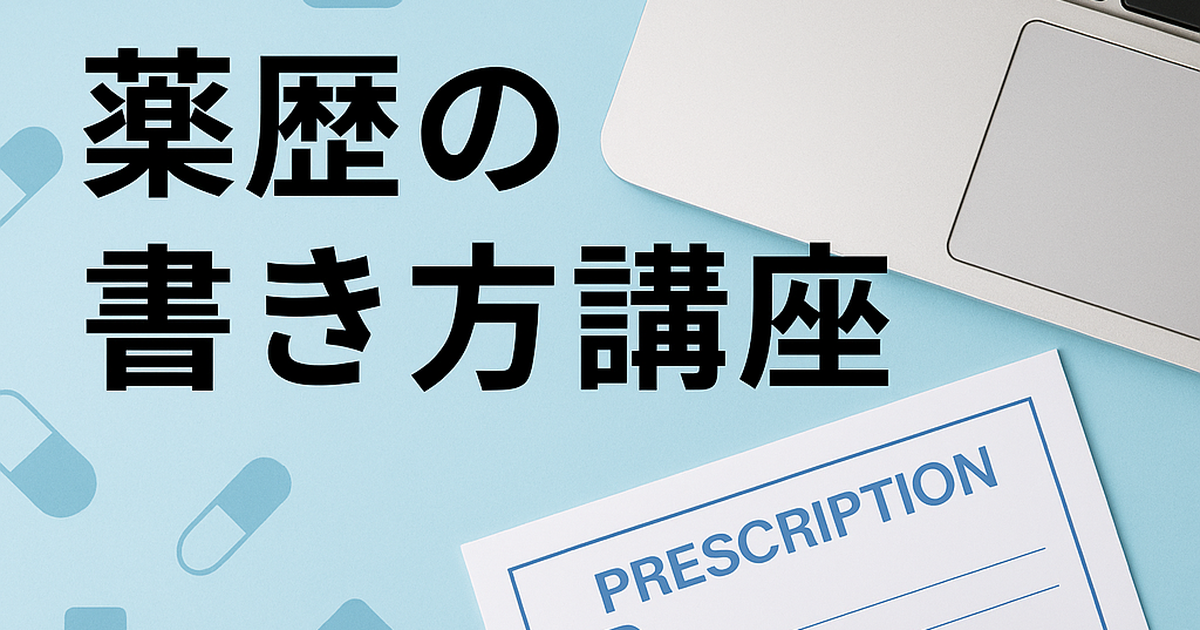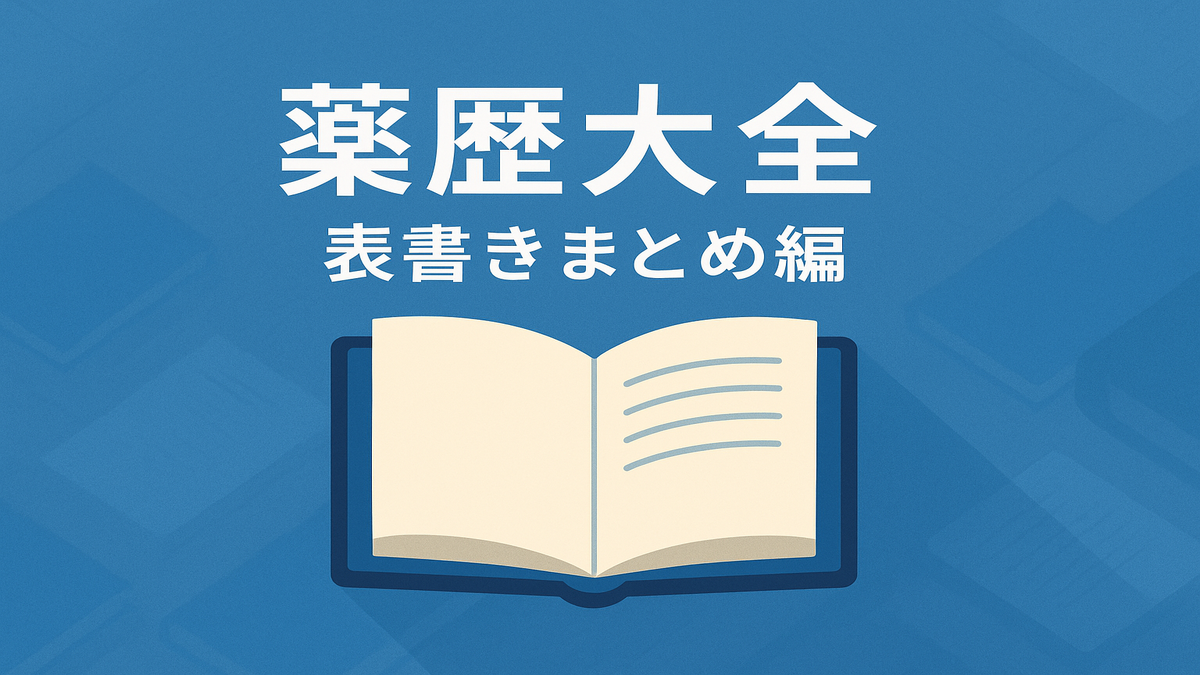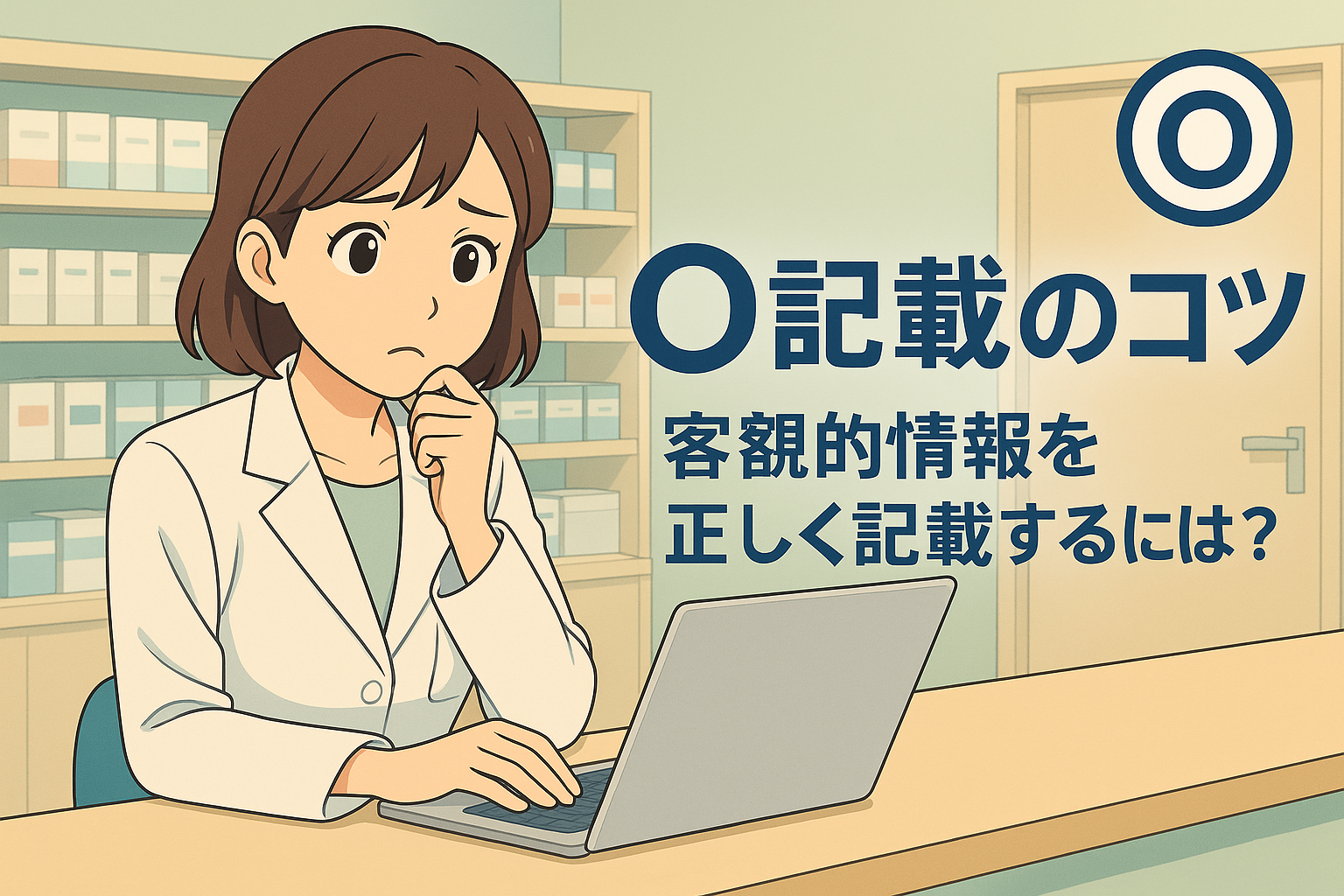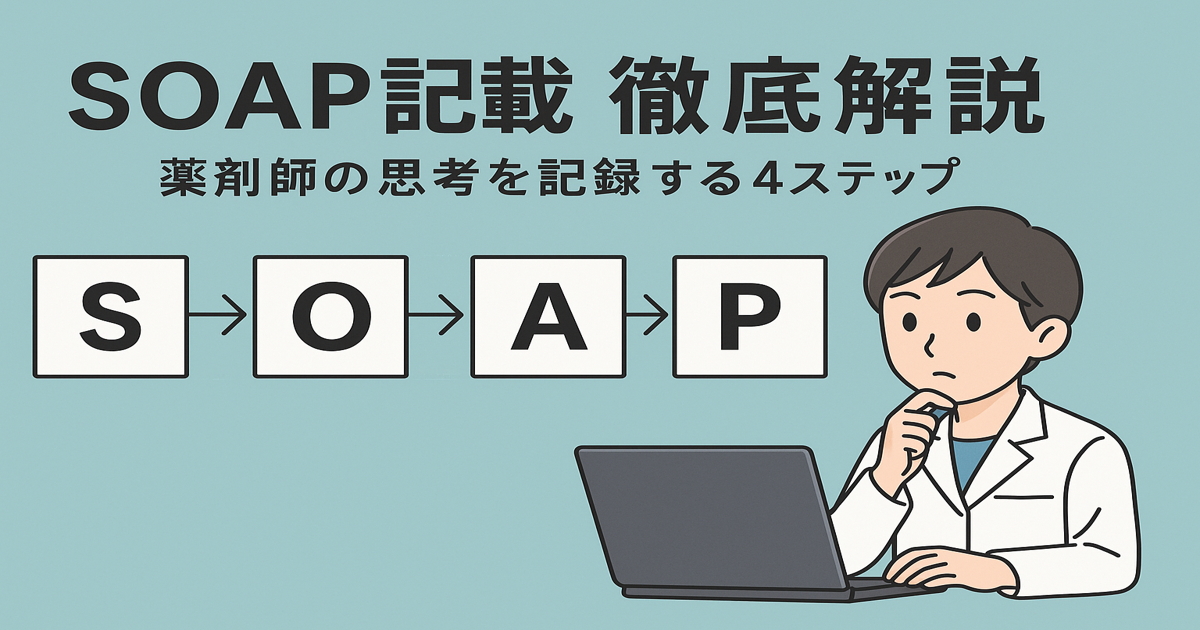【A記載のコツ】薬剤師の苦手を克服する書き方と考え方の基本
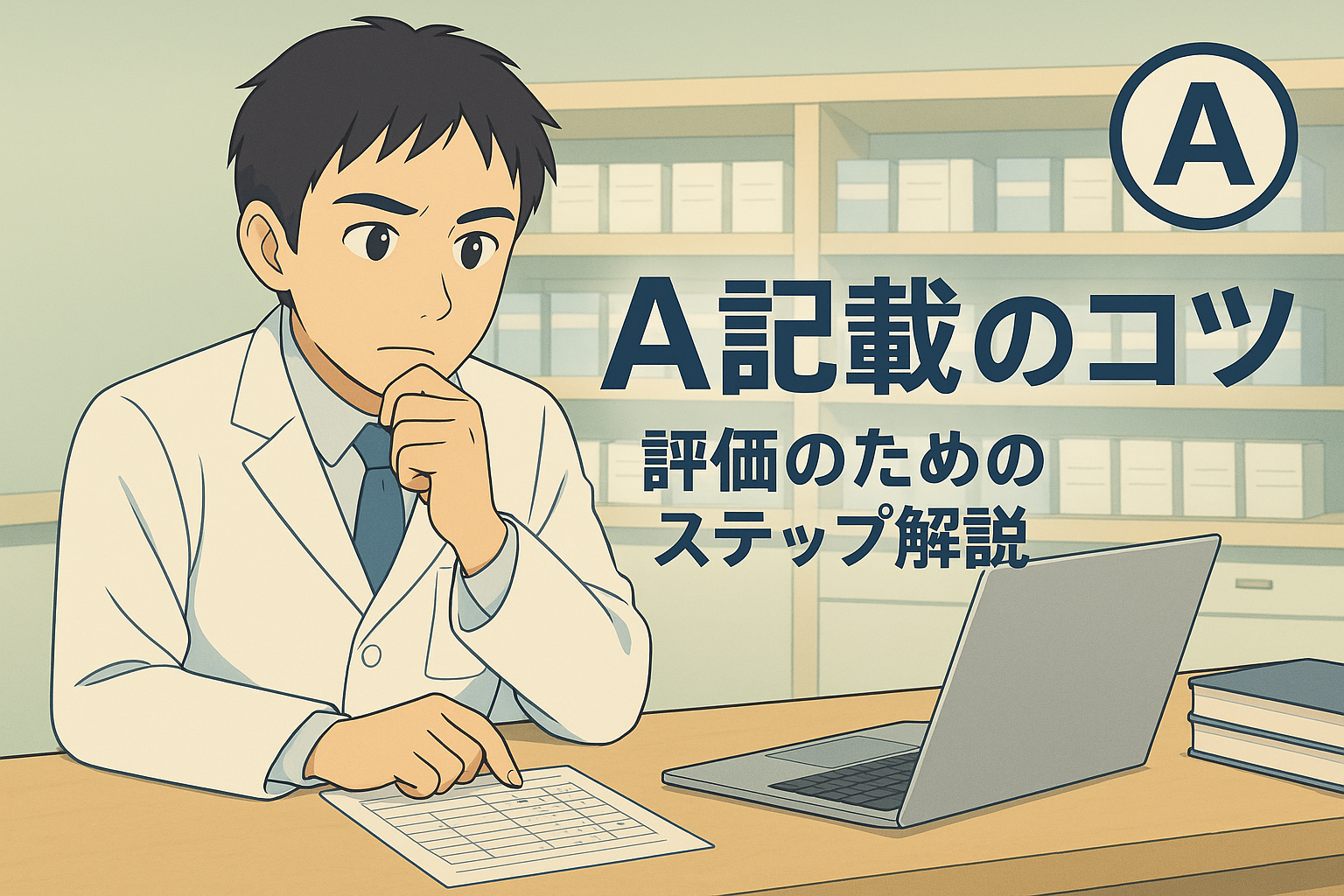
薬剤師の記録に欠かせない SOAP形式。
その中でも「A(アセスメント・評価)」は、S(主観情報)・O(客観情報)をもとに、薬剤師の視点で“評価”を記載する最重要パートです。
この大切な部分を
「継続問題なし」
「特記すべき事項なし」
などの抽象的な表現で終わらせていませんか?
この記事では、
- アセスメントの基本的な考え方
- 押さえておくべき3つの視点
- やりがちなNG記載と改善ポイント
など、薬剤師が現場で使える知識と書き方のコツを丁寧に解説します。
薬歴の質を高めたい方、SOAP記載をより深く理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
まだ前回の記事をご覧でない方はこちらからどうぞ:
- 🔗 【SOAP記載の徹底解説】薬剤師の思考を記録する4ステップ
- 🔗 【S記載のコツ】“患者の言葉”をどう記録する?聞き取りから要約の技術
- 🔗 【O記載のコツ】SOAP形式で薬剤師が“客観的視点”を磨く方法とは?
アセスメント・評価とは?
アセスメントとは、患者から得られた主観的情報(S情報)および検査値などの客観的情報(O情報)をもとに、薬剤師として臨床的な評価を行うプロセスです。
これは服薬指導時に判明した薬物治療上の課題を的確に特定するうえで不可欠な要素となります。
さらにアセスメントは、S・Oの情報を踏まえて具体的な行動・計画(P)へとつなげるための“判断の核”となる部分でもあります。
薬歴全体の記録品質や治療効果に影響を与えるため、専門的な視点と論理的な思考力が求められます。
アセスメントは単なる情報整理ではない
アセスメントには、当日得た情報だけでなく、過去の服薬指導記録や表書きの特記事項も含めて判断する必要があります。
重要なのは、「薬剤師としてどのような評価を行ったか」を残すこと。
情報を整理するだけで終わってしまうと、記録としては意味が薄れてしまいます。
「情報を記録しただけ」で終わらせず、
「この情報から、薬剤師はこう判断した」という視点を添えることが大切です。
情報の整理にとどまらず、評価・判断を言語化する習慣を持ちましょう。
薬剤師として何を書くべきか
記載する際には、単なる事実の列挙ではなく、薬の専門家として“どう考えたか”が伝わる内容にしましょう。
薬剤師としての視点を反映するには:
- 何を評価したか
- どのように判断したか
この2点を具体的に言語化することがポイントです。
ここでは、ありがちなNG記載を2つ紹介し、それぞれの改善策を見ていきます。
❌ 抽象的な評価になっている
評価が曖昧すぎると、後から記録を見返した際に
「どの情報をどう判断したか」が伝わりません。
特に定期処方など変化が少ない場面では、
「特段の変化なし」
「継続上の問題点はない」
といった抽象的な表現に陥りがちです。
こうした場面では、「何について問題がないと判断したのか」を明記しましょう。
例:
- 降圧剤を服用している場合:
→「前回からの血圧変動はなく、血圧管理良好」 - 下剤を服用している場合:
→「便秘症による腹部膨満なし。食事量減少や胃部圧迫も見られず、継続可能と判断」
変化がなかった場合でも、何を確認し、どう判断したかを記録することで、臨床記録としての信頼性が高まります。
❌ 生活背景だけの記載になっている
もうひとつありがちなのが、
生活習慣ばかりを評価して薬剤師としての視点が抜けてしまうパターンです。
たしかに、高血圧や糖尿病では生活療法が治療方針に影響するため、
食事・運動への着目は自然なことです。
実際、SGLT2阻害薬やARBなどには
生活療法を行っても改善しない場合に使用
という条件がついていることもあります。
ただし、そればかりに偏ってしまうと、記録内容が「看護師や栄養士の評価」と変わらなくなってしまいます。
薬剤師である以上、次のような視点を忘れずに評価しましょう:
- 薬の効果
- 副作用の兆候
- 服薬行動・残薬状況
- 相互作用・用法の理解
生活背景と薬剤評価の両面を意識し、
「薬剤師ならではの視点」が伝わる記録を残しましょう。
書き方について|4ステップ思考法
アセスメント記載で迷いやすいのが、
「何から書き始めればいいのか」「どう構成すれば伝わるのか」という点です。
感覚に頼らず、“考える順番”を明確にしておくことで、
記載のブレを減らし、論理的で一貫性のある薬歴を作ることができます。
ここでは、薬剤師が実践しやすい4つのステップに沿ったアセスメントの思考法をご紹介します。
① 問題点の発見
▶目的
最初に行うべきは、「薬剤師として介入すべき問題点の洗い出し」です。
この段階では漏れなく拾うことを重視し、仮説や重複があっても構いません。
後のステップで優先順位や原因分析を行うため、問題点と判断したら網羅的に挙げていきましょう。
▶注意点
- 問題点は「1つの問題につき1文」で簡潔に記載しましょう
- 「体調不良」「様子を見たい」などの曖昧な表現は避け、観察情報や検査値など具体的な情報に基づいて記述してください。
▶記載例
- 「収縮期血圧150mmHgと高値を維持しており、降圧効果が不十分な可能性あり」
- 「残薬が確認されており、コンプライアンス不良が疑われる」
▶補足:見つからないときのチェックリスト
以下の観点を順に確認すると、問題点を発見しやすくなります。
- 薬剤の効果・副作用の有無
- 服薬意義や副作用に対する理解度
- 飲み合わせや用法の理解度
- 服薬状況(残薬の有無、自己管理の状況)
② 原因・背景の分析
▶目的
問題点が見つかったら、次に行うのは「なぜその問題が起きたのか?」という分析です。
同じ問題でも、患者ごとに原因や背景は異なります。
服薬行動・生活習慣・疾患の進行状況・処方変更の履歴など、
多角的な情報からその患者に特有の背景を探ることが大切です。
※問題が多すぎて対応できない場合は、次のステップ「③優先度の評価」を先に実施してもOKです。
▶注意点
- 「この患者に特有の要因は何か?」という視点を必ず持ちましょう
- 先入観にとらわれず、S・Oの情報を丁寧に照らし合わせましょう
- 的外れな分析や機械的な対応は、患者との信頼関係を損なう原因になるので注意しましょう
▶記載例
- 「収縮期血圧150mmHgと高値を維持しており、降圧効果が不十分な可能性がある。服薬コンプライアンスは良好だが、生活習慣の改善には消極的」
- 「服薬必要性を理解しているようだが残薬が確認されており、コンプライアンス不良が疑われる。しかし、すぐに用法変更することに不安を感じている様子」
③ 優先度の順位付け
▶目的
問題が複数あった場合、次に必要なのは優先順位の明確化です。
理想はすべての課題を一度の指導で解決することですが、現実には時間的・心理的制約があるため困難です。
そのため、リスクや重要度の高いものから順に対応する姿勢が求められます。
▶注意点
- 患者の主観的ニーズに流されすぎず、医療的な妥当性を基準に判断
- 優先すべきは、薬学的に見て「重症度が高い」「早期対応が必要」なもの
- 患者の主訴と医療者の見立てが一致しないケースも多いため注意
例:
患者が「痛み止めがもっと欲しい」と言っても、疼痛がコントロールできていればその要望は最優先ではありません。
むしろ「鎮痛薬への依存傾向」が疑われる場合は、依存傾向に対する評価を優先すべきです。
優先順位をつけるときの参考視点
優先度の判断に迷った場合は、以下の4点を基準にしてください:
- 命に関わる、重篤なリスクがあるか(副作用・服薬ミスなど)
- 対応の遅れが予後に影響するか
- 患者にとって実行可能か(継続性・受け入れ度)
- 医師への報告・提案が必要か
これらに多く該当するほど優先度は高いと判断できます。
④ 今後の方針・対応策の立案
▶目的
最後のステップでは、ここまで分析した問題点に対して、どのような方向性で対応すべきかを記述します。
薬剤師の思考プロセスを明示することで、
次の行動・計画(Plan)にスムーズにつながるアセスメントが完成します。
▶注意点
- A(アセスメント)欄では、「どう考えたか」「どのような方向性でアプローチすべきか」を記録します
- 実際の行動(説明・報告・提案など)はP(プラン)欄に記載しましょう
▶記載例
- 「収縮期血圧150mmHgと高値を維持しており、降圧効果が不十分な可能性がある。服薬コンプライアンスは良好だが、生活習慣の改善には消極的。血圧管理には薬物治療と並行して生活習慣改善が必要と判断。補足指導の実施が望ましい」
- 「服薬必要性を理解しているようだが、残薬がありコンプライアンス不良が疑われる。服薬タイミングの見直しによって改善が見込まれるため、今後の指導方針として提案を検討」
まとめ|アセスメント力は薬剤師の“思考力”を伝える技術
アセスメントの記載は、薬剤師にとって単なる記録作業ではありません。
「自分がどう考え、どこに注目して判断したか」を明文化する、“思考の技術”です。
本記事では、以下の3点にフォーカスして解説しました:
- アセスメントはS・Oの繰り返しではなく、薬剤師の視点を明確に残すこと
- 評価には必ず根拠を持たせ、「何を見てどう考えたか」を言語化すること
- 判断と行動を混同せず、考察はAに/行動・計画はPに記載すること
アセスメント記載に苦手意識がある方でも、
今回紹介した4ステップ思考法を活用すれば、誰でも「伝わる薬歴」が書けるようになります。
記録の質が上がれば、介入の質も信頼も、職能発揮も自然とついてきます。
「何となくで書いていたA欄」を卒業し、
“考える薬剤師”としての記録を目指していきましょう。
次回は「P記載の書き方」
次回の記事では、SOAPの最後となる「P(行動・計画)記載のコツ」について、具体的な考え方・構成・表現のコツを詳しく解説していきます。