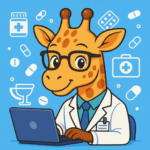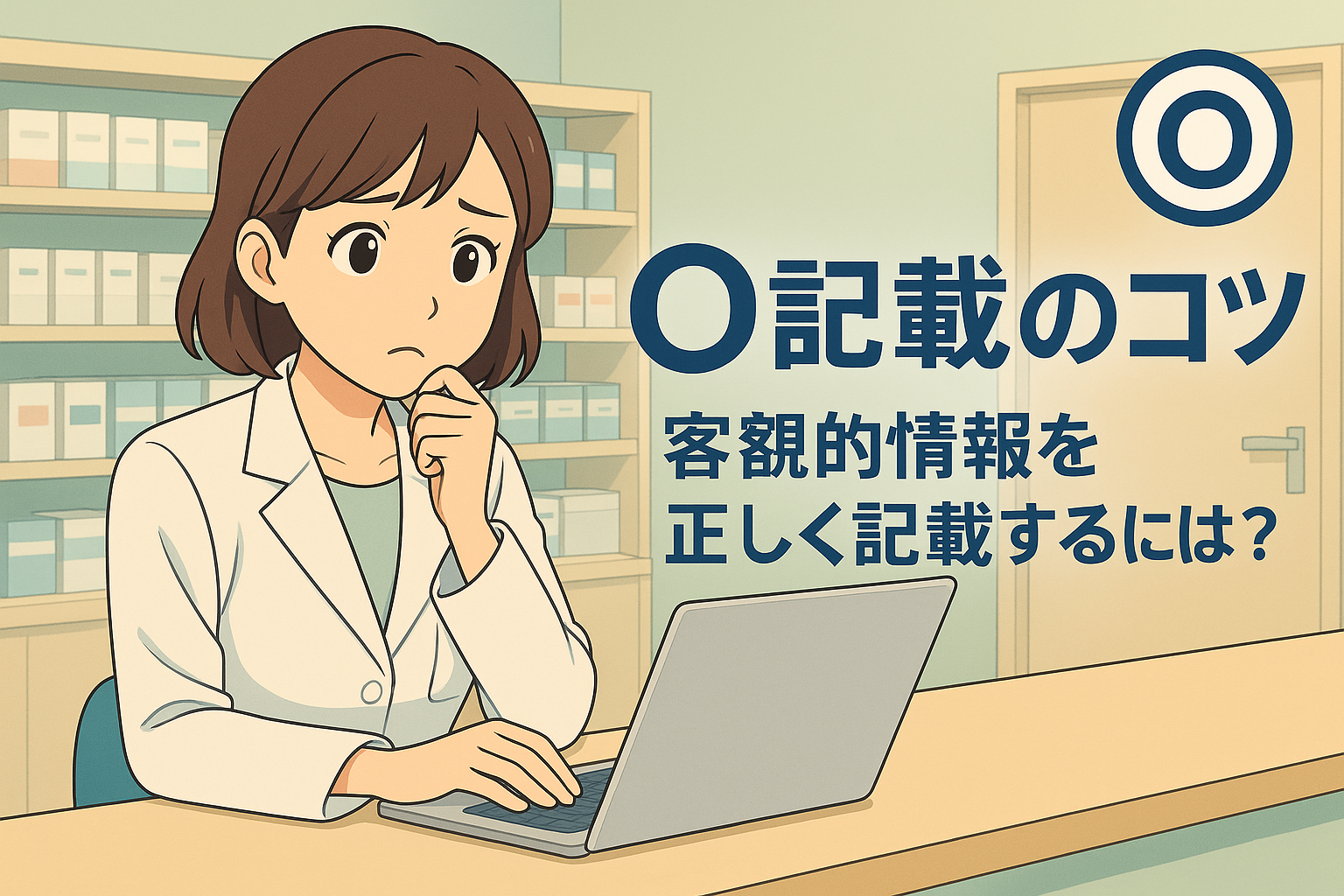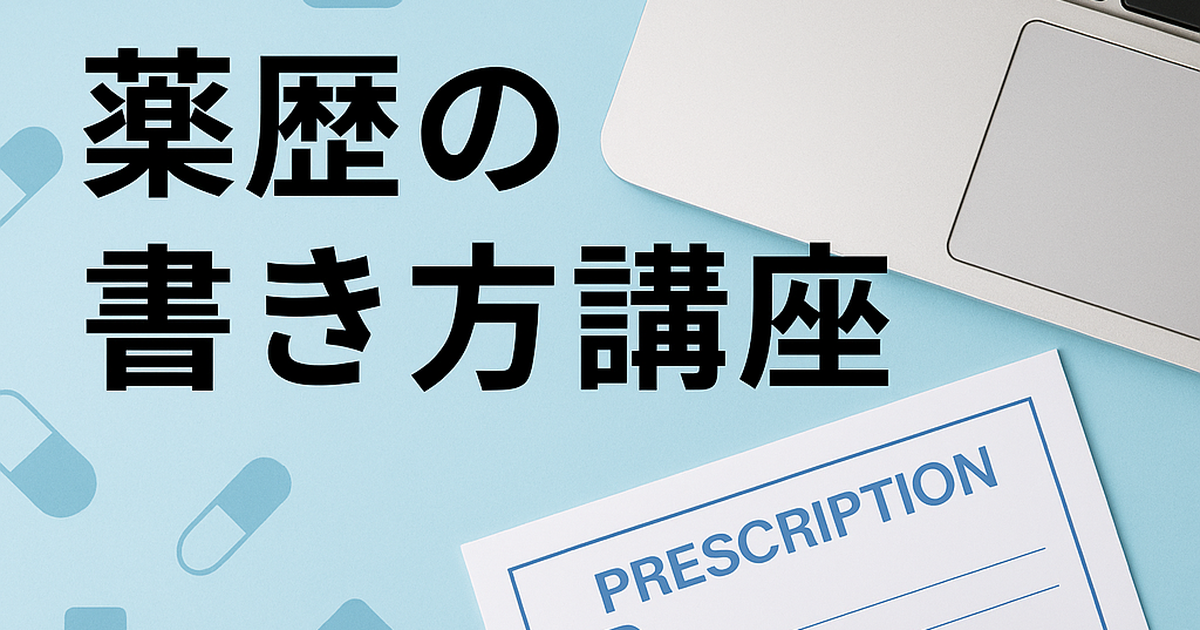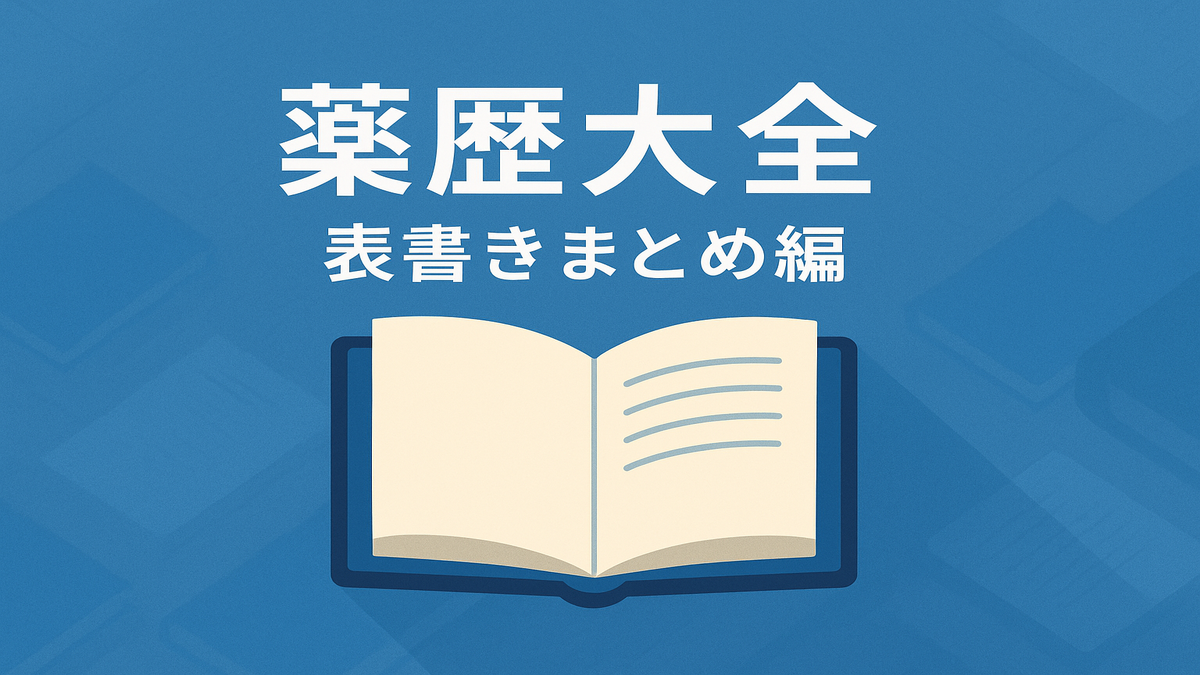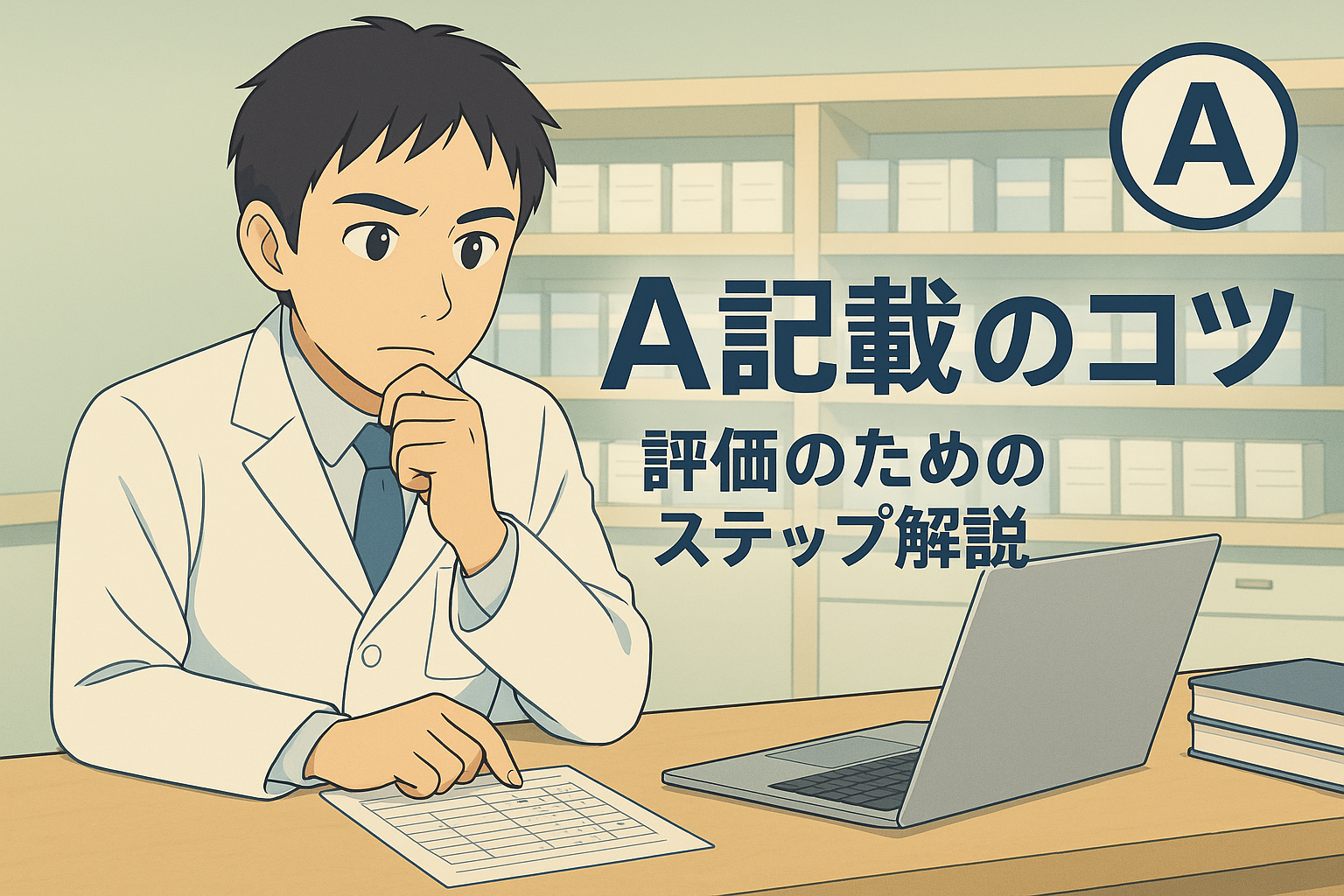【SOAP記載の徹底解説】薬剤師の思考を記録する4ステップ
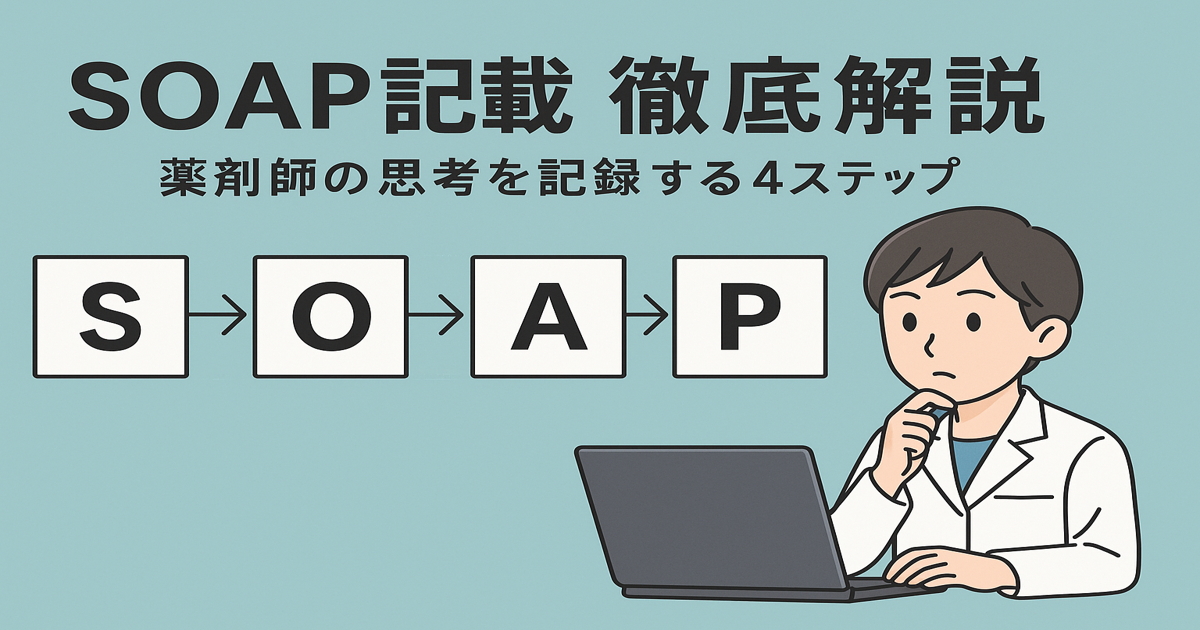
SOPA形式、なんとなく書いてはいるけど…
「これって正しい書き方なの?」
「内容のまとまったSOAPが記載できない…」
「先輩たちに聞いても教えてくれることがそれぞれ違う…」
SOAPを書くときにそんなモヤモヤを抱えながら、日々の指導に向き合っていませんか?
SOAPは単なる記録様式ではなく、薬剤師の“思考”を言語化するためのフレームワークです。
本記事では、SOAPの基本構造と
各構造が果たす役割をわかりやすくステップを踏んで解説します。
この記事を読み終われば、薬歴に対する考え方だけではなく、指導の質も変わります。
今回はまず、「そもそもSOAPって何?」を
改めて確認するところからはじめましょう。
SOAPとは何か?4ステップの概要
SOAPとは、薬歴記載における記録の「型」のひとつです。
必ずSOAP形式で記載する必要はありませんが、現在はこの形式が主流になっています。
この型を学んで誰が見てもわかりやすい薬歴がかけるようになりましょう。
SOAPは主に次の4つの要素から構成されています。
- S:Subjective(主観的情報)…患者さんの訴え、気づきなどの主張
- O:Objective(客観的情報)…観察・検査結果などの結果
- A:Assessment(評価)…薬剤師の考察・判断
- P:Plan(計画)…指導内容や次回対応
この構成は、「情報を整理して→考察して→次の行動につなげる」という
薬剤師に必要な思考の流れを体系立てて記載することができます。
つまりSOAPは、“薬剤師としてどう考えて行動したか”を見える化し、
次のアクションに活かすためのツールです。
このあと、それぞれのパートで
「何をどう書けばいいのか?」を詳しく見ていきましょう。
SOAP形式で記載するメリットと落とし穴
SOAP形式で薬歴を統一する最大のメリットは、
「記録にブレがなくなること」と「思考を見える化できること」です。
メリット3選
● メリット1:記録のブレがなくなり、情報の整理がうまくなる
SOAPには明確な構造があります。
S記載欄には主観的情報、O記載欄には客観的情報…と、
項目ごとに「何を書くべきか」が明確に分かれています。
たとえば指導後に
「患者さんが言っていた内容だからS、検査結果表を持参されたので検査値はO」
と分類して記録していくことで、
自然と情報が整理され、記録の精度も上がります。
また後から薬歴を見返すときも、記録の構造が一定なので必要な情報が探しやすく、
引き継ぎや監査の場面でもスムーズなやりとりができます。
● メリット2:薬剤師の“考え”が見えるようになる
A(評価)やP(計画)は、
薬剤師が「何を考え」「どう行動したか」を記録する欄です。
ここで「判断や行動の意図」を明確に記載することで、
プロフェッショナルとしての姿勢が薬歴から伝わります。
指導の振り返り、他スタッフとの情報共有、個別指導対策――
どの場面においても「考えた根拠・証拠」がある記録は、強い武器になります。
● メリット3:複数回にわたる服薬指導に一貫性が生まれる
服薬指導は継続的に行われ、複数の薬剤師が関わることも珍しくありません。
その中で、SOAP形式によって記録の構造が一定であれば、
「誰が書いても一定の構成で残される」という利点が生まれます。
また、S→O→A→Pの一貫した流れがあるため、
前回の評価(A)や行動・計画(P)を踏まえて、
次回の指導記録を構築しやすくなります。
このように、SOAP形式は“患者との継続的なかかわり”を見える化できるツールでもあるのです。
落とし穴2選
● 落とし穴1:構造だけなぞっても“中身”がなければ意味がない
SOAPの構造に当てはめて記録しただけで、
「あとは自動的に良い薬歴になる」と思っていませんか?
それは大きな落とし穴です。
- Sがただの「〜と言っていた」メモになっていないか?
- Oが「薬剤情報」だけで埋まっていないか?
- Aが毎回「副作用なし」で終わっていないか?
- Pが「用法用量について指導」だけになっていないか?
SOAPはあくまで“思考を伝える型”です。
この型に薬剤師が中身を与えてあげないと、
ただの記録ルーティンになってしまいます。
「なぜそう評価したのか」「なぜ次回も指導が必要なのか」――
考えを込めて書くことで、初めて意味を持ちます。
● 落とし穴2:情報を全部詰め込みすぎてしまう
特に薬歴に不慣れな時期に多いのが、
指導で得たすべての情報をそのまま詰め込んでしまうことです。
たとえば、指導で10個の情報を得たとして、
そのすべてをS・O・A・Pに分けて記載すると、
冗長な記録になり、重要な情報が埋もれてしまうことがあります。
SOAPは「書ける内容を全部書く」のではなく、
“次回以降の指導に必要な情報”を中心に据えることが大切です。
「伝えたい要点をまず決めて、そこに肉付けする」
この意識で記録を構築していきましょう。
次のセクションでは、
各パート(S・O・A・P)ごとに記載のポイントを整理していきます。
SOAP記載の基本とパート別ポイント
各項目の定義と目的、具体例などを整理しました。
復習のために先ほど述べた内容も一部重複させています。
各項目の詳細は別記事にてさらに深掘り予定ですので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。
S(Subjective):主観情報の活かし方
定義と目的:
患者の言葉・訴え・自覚症状など、主観的に得た情報を記録するパート。
具体例:
「飲みにくい」「体がだるい」「たまに飲み忘れる」など
書き方のコツ:
- 患者の言葉をできるだけそのまま記録する
- 感情や不安など、数値化できない情報も含める
- 記録者(薬剤師)の主観を交えず、事実ベース(患者主訴)で記載する
O(Objective):客観情報の正確な整理
定義と目的:
検査値、身体所見、服薬状況など、客観的な事実を記録
具体例:
HbA1c 7.2%、血圧 136/84、薬が余っている状況など
書き方のコツ:
- 検査日や情報源(検査票、患者持参メモなど)などの根拠を明記
- 情報に編集を加えず、ありのままを記録
- 前回までの記録を基にした治療回数や経過(例:ピロリ菌除菌歴)も追記
A(Assessment):薬剤師の思考を可視化する評価
定義と目的:
SとOに記載した情報を踏まえて、薬剤師の判断や仮説を示す
具体例:
「副作用の可能性は低い」「コンプライアンス不良の可能性あり」など
書き方のコツ:
- 「〜の可能性」「〜のリスクがある」といった仮説を含める
- 他の選択肢との比較や、なぜその判断に至ったかの理由も添える
- SOAPの中でも最も“薬剤師らしさ”が出る部分なので、簡略化しすぎない
P(Plan):次に何をするかを具体的に書く
定義と目的:
評価を受けて行った指導、今後の計画、次回の確認事項を記録する
具体例:
「患者の理解を確認し、次回も継続指導」「医師へ電話連絡予定」など
書き方のコツ:
- 「具体的にどう動いたか・どう動くか」を書く
- 「継続指導」だけではなく、対象と内容を明確に
- チーム内共有や次回指導につなげることを意識
SOAP記載でよくある疑問5選
SOAP形式で薬歴を記載する際、多くの薬剤師が共通して抱く悩みや混乱があります。
ここでは、現場でよく挙がる5つの疑問について、実践的な視点から一つずつ丁寧に答えていきます。
Q1:SとOってどうやって区別すればいいの?
患者の発言と観察結果が混ざってしまって、記載場所にいつも迷います。
A:
Sには「患者が発言した内容(主観的情報)」、
Oには「薬剤師が確認した事実・データ(客観的情報)」を記載します。
このとき、患者の主張と実際の事実が食い違うケースでは、
両者を正しく分けて記録するのがポイントです。
例:
S:家に残ってる薬はないです
O:受診間隔より14日分の残薬があるはず
A:主訴と受診状況に齟齬あり。薬剤紛失の可能性
このように、SとOを明確に切り分け、Aで薬剤師の評価を加えることで、
判断の流れが伝わりやすくなります。
Q2:SOAP全部書こうとすると、毎回すごく時間がかかるんですが……
A:
以下の3つのポイントを意識するだけで、大幅に時間を短縮できます。
- ブラインドタッチを習得する
タイピングスピードが記録の効率に直結します。
私自身、ブラインドタッチができなかった頃は薬歴残業が慢性化していました。
しかし習得後は、指導中にSを打ちながら患者の顔を見ることもでき、記録も圧倒的に楽になりました。 - 話した内容を全部書こうとしない
新人時代に陥りがちなミスです。
良い薬歴は“情報量”ではなく、“要点の伝達力”で決まります。
服薬指導の前に「今日の問題点は何か?」を意識すると、記録の質も自然と上がります。 - 表書きを活用する
SOAPで繰り返し記載される患者情報(既往歴や生活背景など)は、
表書きにまとめておきましょう。SOAPは「今回の指導に必要な情報」だけに絞れ、記録の重複が減ります。
Q3:A(アセスメント)って、いつも「特になし」で終わっちゃう……
A:
「特になし」と書いてもOKですが、“何が特になしなのか”は必ず明示しましょう。
例:処方薬:ロキソプロフェン錠の場合
- 鎮痛効果の評価(効いているか)
- 有害事象の有無(胃腸障害・腎障害)
- 服薬状況(自己判断での休薬など)
具体的なA記載の例:
疼痛コントロール良好、薬学的介入点は特になし
服薬遵守良好、服薬管理上の介入は特になし
胃腸障害・腎障害の所見なし、継続使用上の問題は見られず
Q4:P(プラン)には「継続指導」「特記事項なし」しか書いてません
これじゃだめですか? 評価されないって本当ですか?
A:
残念ながら、それでは評価されません。
個別指導において「継続指導」や「特記事項なし」が連続すると、
薬学的管理料などの返戻対象(報酬の返金)になることがあります。
これは単なる収益問題ではなく、
薬剤師の介入が見えない記録として判断されてしまうためです。
どう改善するか?
「継続指導」だけでなく、何を確認・指導したのかを明記しましょう。
例:
継続指導(血圧測定継続・記録方法の確認指導済み)
Q5:「一包化」「残薬」みたいな話って、どこに書くべき?
S?O?それともP? 情報の置き場所にいつも迷います。
A:
結論から言うと、ケースごとに記載場所が変わります。
ただし、店舗内での記載ルールを統一しておかないと、
情報の共有や監査時に支障が出ます。
記載場所の一例:
- 一包化について
・必要性(なぜ必要か):A欄(薬剤師の評価)
・実施内容(どんな形で提供したか):P欄
・印字確認や実物の確認:O欄 - 残薬について
・患者が口頭で説明:S欄
・残薬を薬剤師が数えた:O欄
・日数計算から推定された残薬:O欄に記録し、A欄で評価
最後に:
一包化や残薬は、患者支援に直結する重要な情報です。
対応の根拠や判断プロセスを明記しておきましょう。
記載場所に迷ったら、まずは管理薬剤師と相談してルール化しておくのがおすすめです。
まとめ:SOAPは「書く」ことで薬剤師の思考を鍛えるツール
SOAP形式は、単なる記録の“型”ではありません。
主観・客観・評価・計画という構造を通じて、薬剤師の思考と判断を可視化する道具です。
今回の記事では、SOAP記載のメリットや、
現場でよくある疑問・つまずきポイントを整理しました。
✅ 型に沿って書くことで…
- 記録のブレがなくなる
- 薬剤師の考えを見える形にできる
- 継続的な服薬支援が一貫して記録できる
⚠ 一方で、注意すべきポイントも…
- 構造だけをなぞった“中身のないSOAP”
- 情報を詰め込みすぎた読みにくい記録
だからこそ大事なのは、「型に思考をのせる」こと。
SOAPは、あなたの専門性を記録に落とし込むための
思考トレーニングの場でもあります。
明日からの薬歴に、ほんの少しの意識を加えるだけで、
あなたの記録は、伝わる・つながる薬歴に変わっていきます。
続けてはこちら!
▶ 【S記載のコツ】“患者の言葉”をどう記録する?聞き取りから要約の技術
S記載のコツをぎゅっと詰め込みました。ぜひ続けてご覧ください。