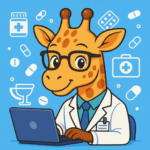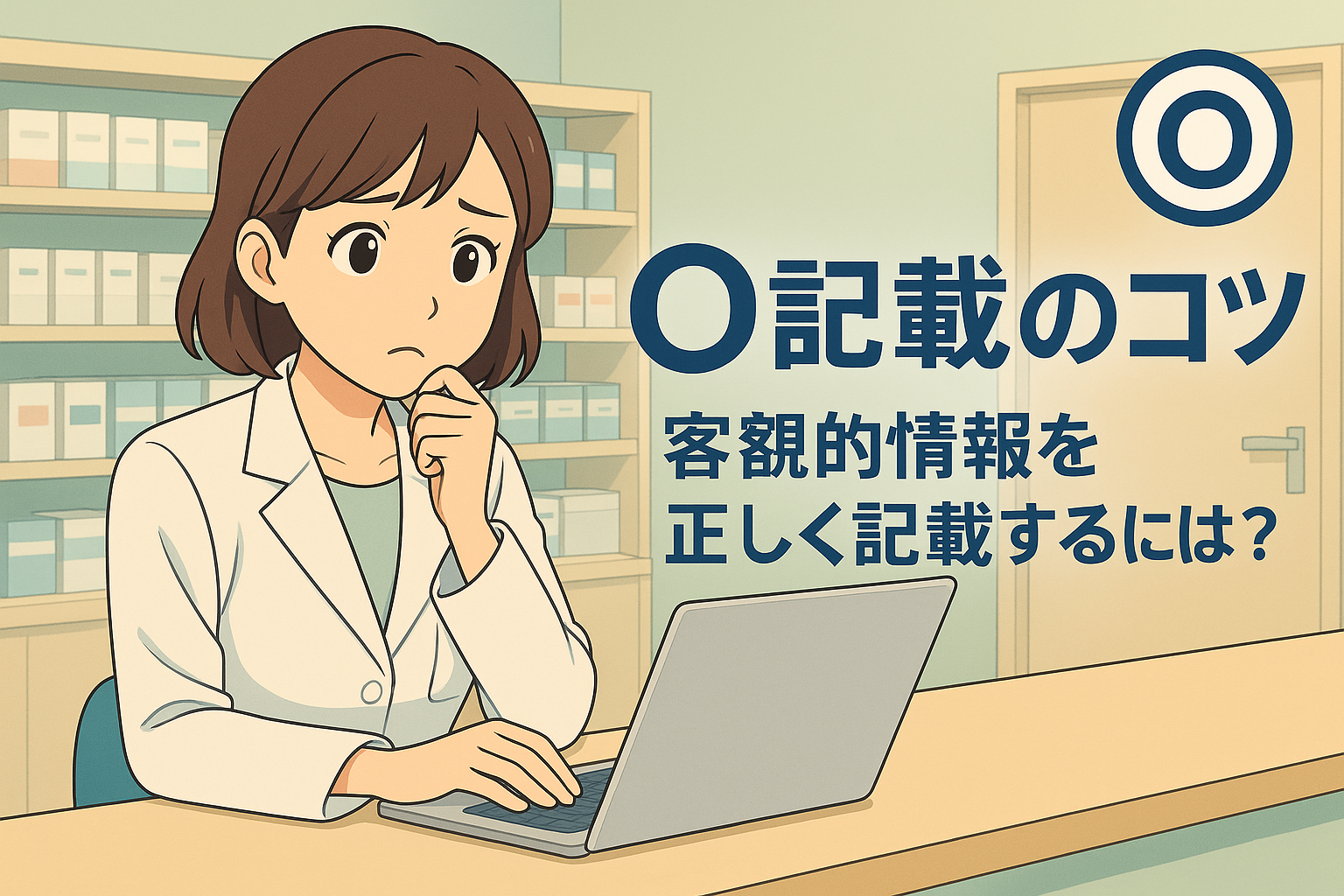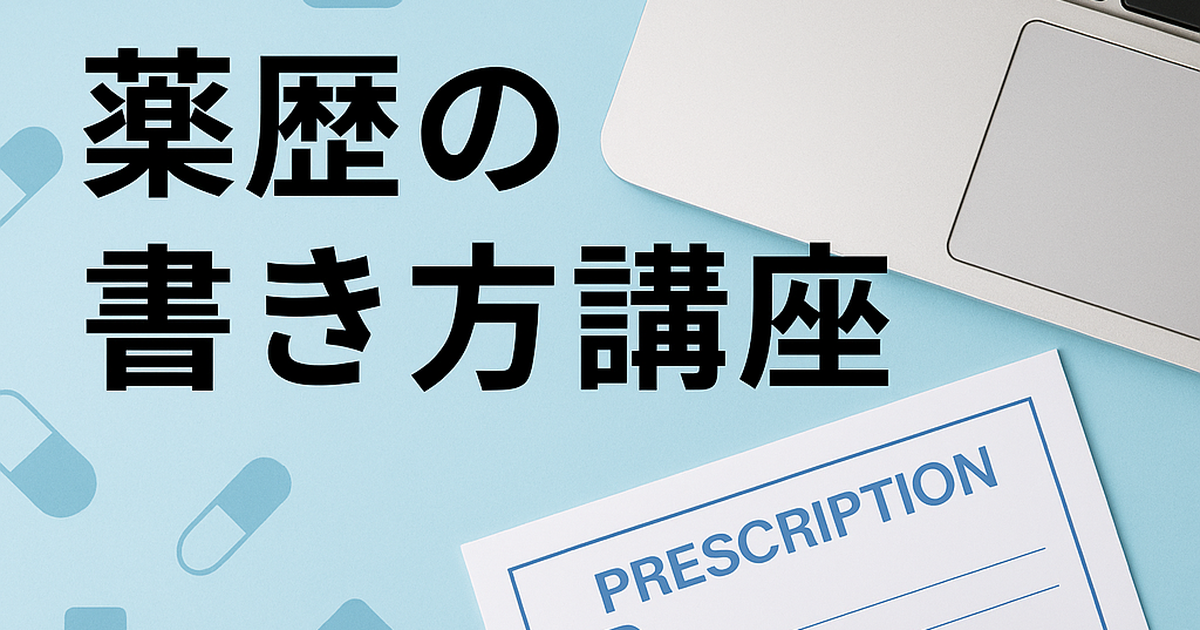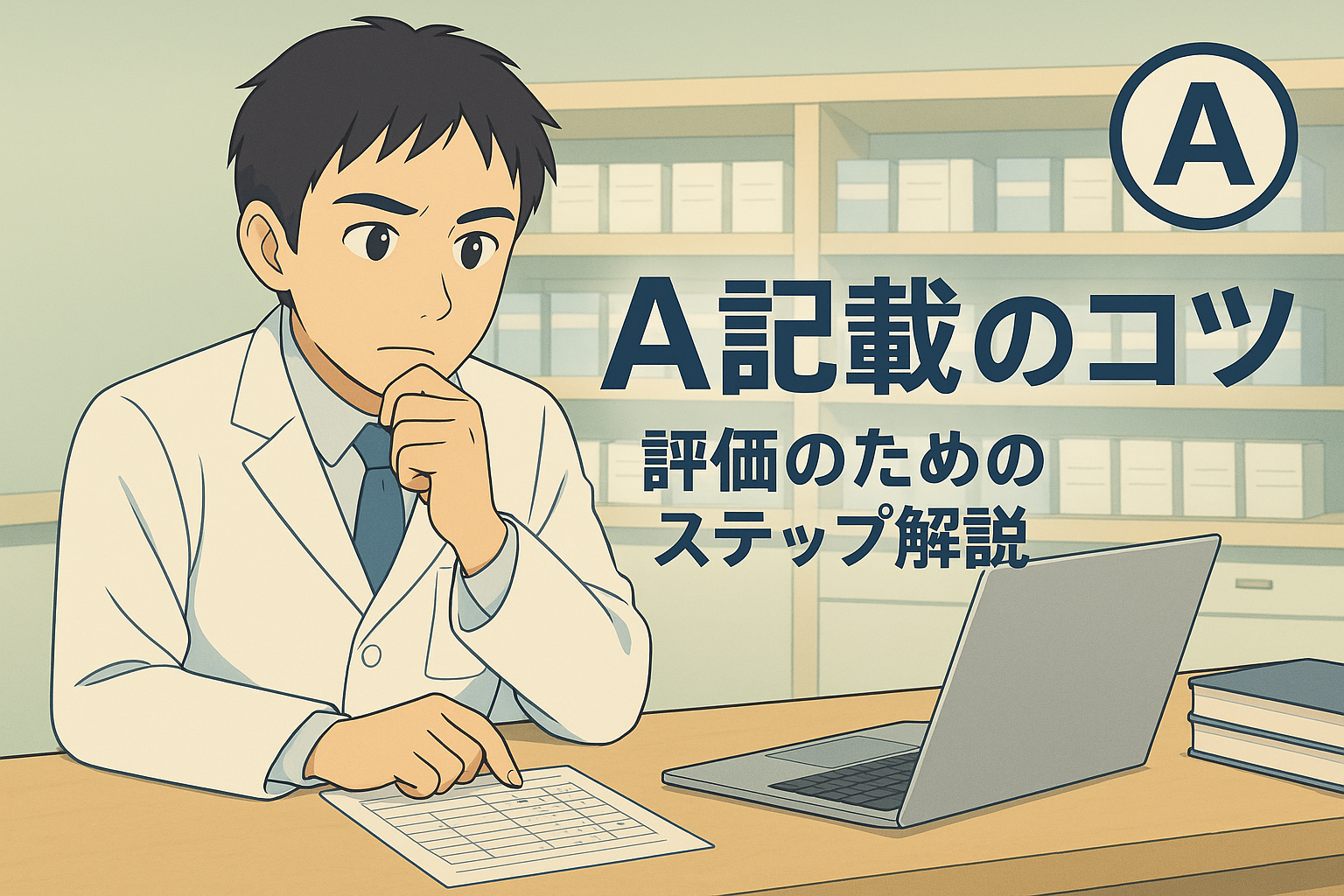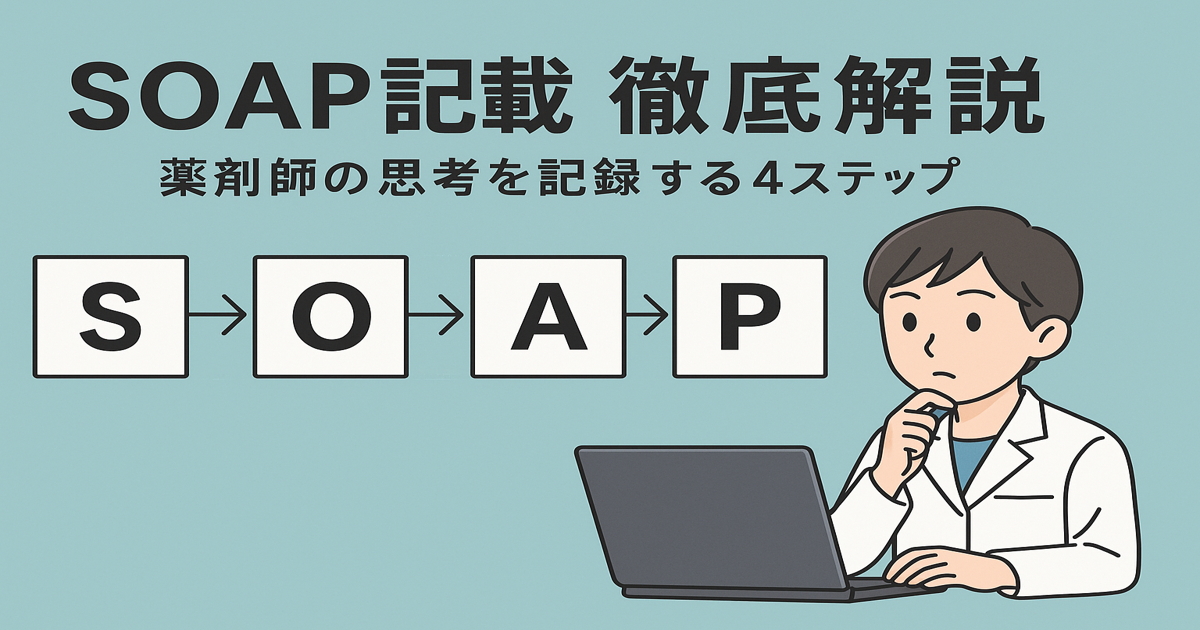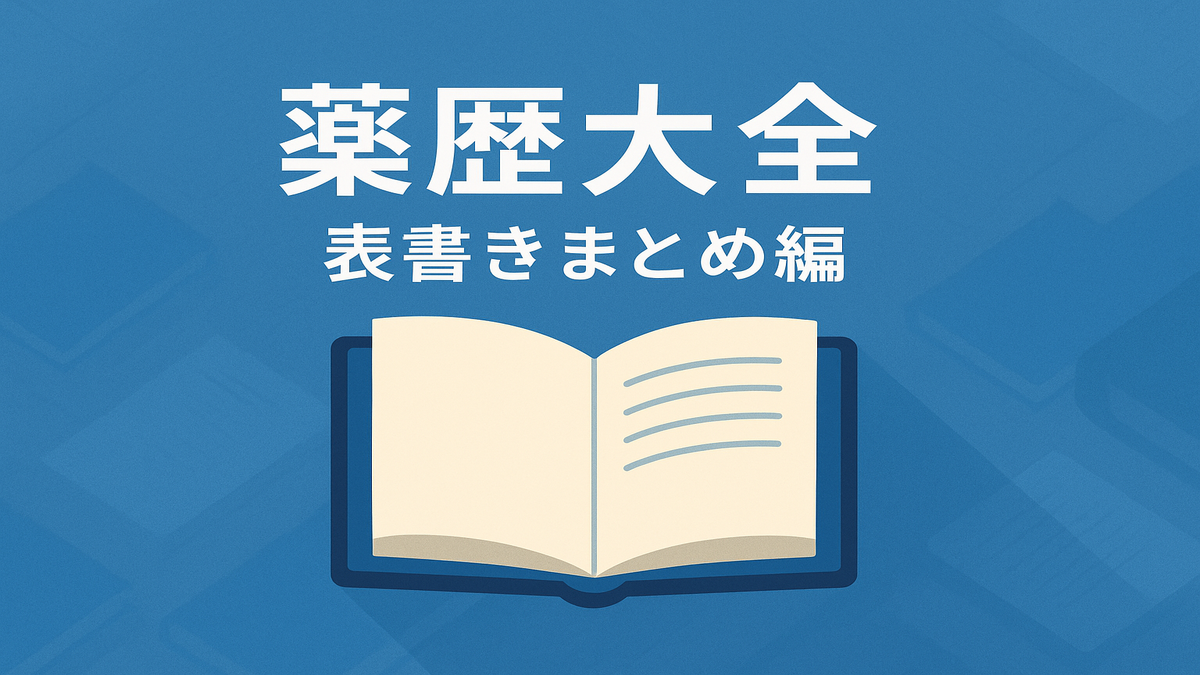【S記載のコツ】“患者の言葉”をどう記録する?聞き取りから要約の技術

S欄の質は、薬歴全体の精度に直結します。
だからこそ、なんとなくの記載で済ませず、“情報の引き出し方”から見直すことが大切です。
この記事では、よくあるNG例、記載の工夫、聴き取りのコツ、記録例を通して、S記載スキルの底上げをサポートします。
前の記事を読んでない方はこちらから
【SOAP記載の徹底解説】薬剤師の思考を記録する4ステップ
S記載とは?その役割と重要性
S欄は、患者さんが「感じたこと」や「話してくれたこと」を記録する場所です。
言ってみれば、薬歴のスタートライン。
ここがあいまいだと、あとから薬歴を見返したときに
「この人、どんな様子だったっけ?」と分かりづらくなってしまいます。
「そのまま書けばOK」はNG
ありがちなのが、
「患者さんの言葉をそのまま書けば十分」と思ってしまうパターンです。
でも実際は、言葉の裏にある背景や気持ちを
少しだけ深掘りして記録することが、より質の高いS記載につながります。
たとえば、こんな場面
患者さん:「最近、頭が痛くて…」
この一言だけで終わらせるのではなく、
- いつから?
- どんな痛み?
- 生活にどんな影響が出ている?
と、少し踏み込んで話を聞いてみましょう。
それによって、薬の副作用か? 他の病気か?
といった判断材料が得られる可能性があります。
S欄は「聴く力」×「気づく力」
良いS記載とは、「聴いたこと」+「背景に気づいたこと」のセットです。
ここをしっかり書けると、
その後の O(客観)・A(評価)・P(指導) も書きやすくなります。
まずは、“ただ聞いたこと”ではなく、
“気になったこと・背景まで”をS欄に記録するイメージを持ってみましょう。
よくあるNG例とその理由
S記載が「うまく書けない」と感じること、意外と多くありませんか?
その原因のひとつは、無意識にやってしまっている“NG記載パターン”に気づいていないことです。
ここでは、現場でありがちなS欄のNG記載を3つ紹介します。
それぞれ「何が惜しいのか?」「どう改善できるか?」を一緒に見ていきましょう。
⚠️ よくあるNG例3選
- NG①:「特になし」「体調変わらず」で終わっている
- NG②:患者の言葉をそのままメモするだけ
- NG③:「なんとなく聞くだけ」で情報が拾えていない
NG①:「特になし」「体調変わらず」で終わっている
長期服用中の患者さんに体調確認したとき、
「いつも通りです」「特に変わりないです」
と言われること多いですよね。
でも、そのままS欄に書いて終わってしまうのは非常にもったいないです。
患者さん自身が変化に気づいていなくても、
実際には副作用や病状の変化が隠れていることがあります。
▼ こんな質問を添えてみましょう:
- 「肩こりが前より強くなっていませんか?」
- 「最近、咳が出やすくなったと感じることは?」
「変わらない」の中にある“違和感”を拾い上げることがポイントです。
それが、質の高いS記載への第一歩です。
NG②:患者の言葉をそのままメモするだけ
「主訴をそのまま書くことが大切」と教わった人も多いでしょう。
でも、聞いた言葉だけを書くだけでは“記録の意味”が薄れてしまうこともあります。
▼ よくある記載パターン
パターン①:問診の受け売り
- 「先生が大丈夫って言ってたんで」
- 「変わりないって言ってたので問題ないと思います」
パターン②:患者の一方的な意見
- 「薬は家族が管理してるから分からない」
- 「医者に聞いたからもういいでしょ」
確かに、このような発言をする患者さんがいるのは事実です。
しかしこれだけでは、薬剤師がどう関わったか、何に気づいたかが
まったく見えてきません。
薬歴は「薬剤師が考えて記録として残す」ことができる公的な文章です。
患者の発言をベースにしながらも、
背景や補足、気づいたことを書き加えることで、記録の価値がグッと上がります。
NG③:「なんとなく聞くだけ」で情報が拾えない
声かけをする際、「とりあえず体調を聞く」だけになっていませんか?
そのまま雑談のように終わってしまい、
S欄に書ける内容がほとんどないという事態に。
実はこれ、「今日この患者さんに何を知りたいのか?」
が明確になっていないことが原因です。
▼ たとえば:
処方変更があった患者に対して、
「最近どうですか?」だけだと「まあまあです」で終わりがち。
そこで一歩踏み込んで、「眠気やふらつきは感じませんでしたか?」など、“目的を持った質問”をすることで記録に残せる情報が自然と出てきます。
S記載は、「聴いたことを書くだけ」ではなく、
「どんな情報を引き出すか」を意識することから始まっています。
S記載が上手くなる3つのコツ
① OPQRSTを意識する
問診技法のひとつに、「OPQRST」という考え方があります。
これは医師が症状を聴く際に使うフレームで、以下の6項目で構成されています:
- O(Onset): いつから症状が出たか
- P(Provocation/Palliation): 何で悪化・軽快するか
- Q(Quality): どんな性状か(ズキズキ・ズーンなど)
- R(Region): どこに症状があるか/どこへ広がるか
- S(Severity): 症状の強さ(程度)
- T(Time course): 経過・変化の仕方
これらを意識して患者さんに聴き取りをするだけで、
漠然とした訴えが、明確で記録しやすい情報へと整理されていきます。
▼ たとえば:
患者:「最近、頭が痛くて…」
薬剤師:
- 「いつからですか?」(O)
- 「どんな痛みですか?」(Q)
- 「何かすると悪化しますか?」(P)
OPQRSTに沿った質問をすることで、S欄に記録する内容にも芯が通ります。
ぜひ、明日から活用してみてください。
② 生活・家族・心理の背景まで意識する
服薬指導は、薬の説明をするだけでは不十分です。
指導時にはその人全体(生活・家族・心理状況)を理解する視点が求められます。
▼ たとえば:
- 「夜中にトイレが近い」
→ 独居高齢者で転倒リスクに不安 - 「飲み忘れが多い」
→ 介護疲れで生活リズムが乱れていた - 「薬が怖い」
→ 家族にがん患者がいて薬への不信感がある
このような背景は、何気ない会話の中から自然に引き出せることが多いです。
単に「症状を聞く」のではなく、
「なぜそう感じているのか?」
「生活にどんな影響があるのか?」
という視点で聴くことで、より深いS記載が可能になります。
③ オープン質問→クローズド質問の順番を意識する
S情報を上手く引き出せないとき、「質問の順番」が鍵になります。
ここで役立つのが、オープン質問とクローズド質問の使い分けです。
オープン質問: 自由に話してもらう質問(例:「体調どうですか?」)
クローズド質問: 「はい/いいえ」で答える質問(例:「眠気はありますか?」)
おすすめの流れ:
- まずオープン質問で幅広く情報を引き出す
- その後、クローズド質問で絞り込み・確認
▼ 実例:
- 薬剤師:「ここ最近の体調はどうですか?」(オープン)
- 患者:「まあまあですかね…ちょっと疲れやすくて」
- 薬剤師:「ふらつきや眠気は出ていませんか?」(クローズド)
このように会話の流れを意識すると、
記録に残すべきS情報が自然と明確になります。
「どう聞くか」が「どう記録できるか」を決めます。
質問の順番を意識するだけで、S欄の深みが大きく変わってきますので是非活用ください。
記載例(ビフォー/アフター)
ここまでS記載のポイントを学んできました。
では実際に、「頭痛」をテーマにした記載例を見ながら、どこが惜しいのか・どう改善できるのかを一緒に確認していきましょう。
❌️悪い例:「特になし」「頭痛あり」などの記載
S:頭痛はあるけども、普段通りで特に変わったことはない。
▼ なぜ悪いのか?
- 「普段どおりだけ」では簡潔すぎて情報が曖昧
- 「頭痛」がどんな痛みか不明
- 頻度・性状・経過などが抜けている(=OPQRSTが活かされていない)
このような記載では、あとから見返しても患者の状況が分からず、O(客観)・A(評価)・P(指導)にもつなげにくいです。
⭕️ 良い例:具体的+背景・理由も含まれる記載
S:頭痛は週に3回程度。前頭部を中心にズキズキする痛み。
特にパソコン作業中や勤務後に悪化する傾向がある。
市販の鎮痛剤を服用すると30分ほどで軽快する。
痛みによるストレスや睡眠不足もあり、不安を感じている様子。
▼ なぜ良いのか?
- OPQRSTに沿って症状が具体的に描写されている
- 生活背景(PC作業・勤務後)が明記されている
- 「不安」「ストレス」といった心理的要素も含まれている
このように記載できると、次のO・A・P記載への展開が非常にスムーズになります。
薬剤師の質問力と観察力次第で、ここまで深い情報が引き出せるのです。
まとめ:S欄は“ただのメモ”ではなく“考える材料”
「何もなかった」と言われたとしても、
その“何もない”をどう聴き取るかで薬歴の価値は大きく変わります。
また「頭痛あり」と書くだけで終わらせず、
いつ・どこで・どんなふうに・なぜそう感じたかまで具体化する意識が重要です。
S記載は、患者の言葉を記録する場であると同時に、薬剤師としてどう考えるか、行動するかを導き出す材料でもあります。
日々のやりとりに、ほんのひとつ質問を加えるだけで、薬歴の深さと信頼性はグッと高まります。
背景まで汲み取る姿勢が、あなたの記録を“伝わる薬歴”へと変えていきます。
まずは、ひとつの声かけから。明日の現場でぜひ試してみてください。